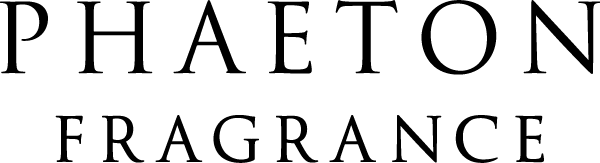儚さをまとう「KAKIGORI」の美学
「KAKIGORI」という名の香り。
それは、肌にふれた瞬間、雪のようにすっと溶けていく。
OBVIOUS Parfumsが表現したのは、ひと匙の氷に宿る、日本独自の“儚さ”の美学。
ただ冷たいだけではない、“氷の詩”を香りでまとう体験です。

「削り氷に甘葛かけて、新しき金椀(かなまり)に入れたる」
平安時代、清少納言が『枕草子』に記したこの一節は、日本最古のかき氷の記録として知られています。
冬に切り出した天然氷を氷室に蓄え、夏になってようやく味わう——。
それは貴族たちだけが味わうことのできた、“時を超えた涼”でした。
この氷は、「氷室(ひむろ)」と呼ばれる土中の貯蔵庫で、大切に保管されていました。光を閉ざし、湿り気を帯びた静かな空間の中で、氷はじっと夏を待っていたのです。
当時の人々にとって氷は、ただの涼ではなく、“時”そのものを閉じ込めた、神聖な存在でした。
この“時を閉じ込めた”という感覚は、香りのあり方ともどこか重なります。
香水瓶の中で眠っていた香りが、肌にふれた瞬間、記憶とともに時を解き放つ——その繊細な瞬間に、氷と香りは静かに共鳴しているのです。
かき氷は、冷たさだけでなく、時間とともに移ろう“かたち”の芸術でもあるのでしょう。
削られた氷が、器に舞い落ちる音。
口に含んだ瞬間、広がる冷気。
そして、すぐに姿を消す潔さ。
それは、まるで桜の散り際のような“無常”の美なのです。

現代でも、かき氷は形を変えながら、人々の夏を彩り続けています。
屋台で楽しむ懐かしい風味もあれば、素材や削りにこだわり、まるで和菓子のように洗練された表現に出会えることも。
どちらも、ひと匙の氷に宿る記憶を呼び起こし、私たちの感覚を豊かに揺らすものです。
なかでも印象的なのは、削り方が生み出す“余白”。
ふわりと空気を含んだ氷は、口にしたとたんに消え、そこに静けさと「間(ま)」を残します。
その余韻こそが、味わう人の心をふるわせるのです。
この「重ね」と「余白」の感覚は、香りにも通じるのではないでしょうか。
たったひと吹きで、時間や空気の流れまでもが変わっていく。
香水とは、身体と呼吸の中で詩のように展開する芸術なのです。
OBVIOUSの「KAKIGORI」コレクションは、そんな五感の旅を香りで描き出します。

White Crush(ホワイトクラッシュ)
氷のように透明で、繊細。
アイリスとホワイトムスクが奏でる、静かな清涼感は、朝の雪景色のよう。
肌にふれた瞬間、音もなく溶けていくその感覚は、まさに“涼の詩”。

Dulce de Leche(ドゥルセ・デ・レチェ)
キャラメルとミルクの甘さが、氷の上にゆっくりと溶け出す午後の光。
とろけるような温もりと、ほのかなコクが重なり、
ノスタルジックな幸福感を残します。

Plum Cream(プラムクリーム)
梅の塩気と果実の奥行きが、意外性のあるアクセントに。
まるで夜風にふと漂う香りのように、深く、ゆったりと広がります。
香りを重ねることは、かき氷に蜜を注ぐ瞬間のよう。
レイヤリングによって香りが変化していく体験は、氷が溶けていく時間の中で味が移ろう「かき氷」と重なります。
それは、肌の上でしか出会えない香りの風景。
香りをまとうことは、一瞬の季節を、そっと自分自身の中に閉じ込めることなのかもしれません。

「KAKIGORI」は、千年前の貴族たちが愛した“涼の美学”を、現代の香りとして呼び覚ますコレクション。
ひと匙の氷が、時を越えて、今、あなたの感覚の奥へ、静かに届きます。